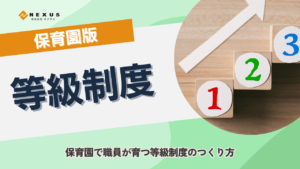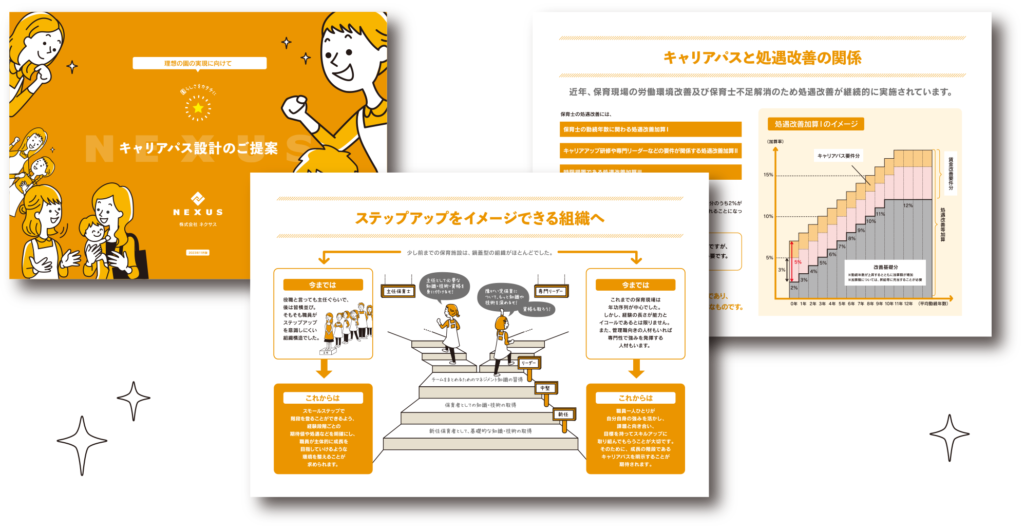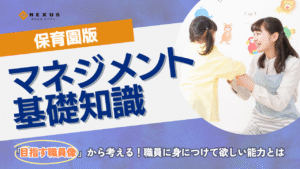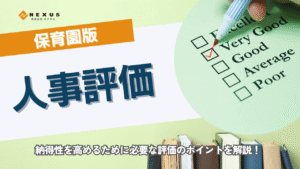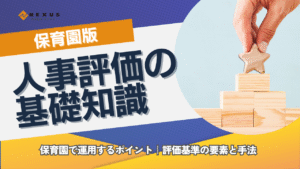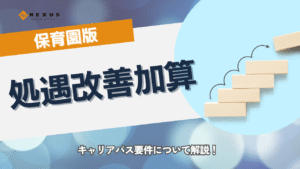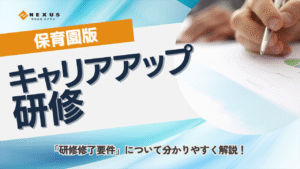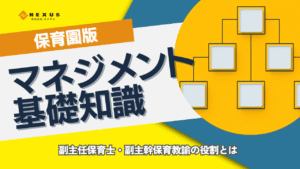保育園の人事評価|職員のモチベーションを高める人事評価とは
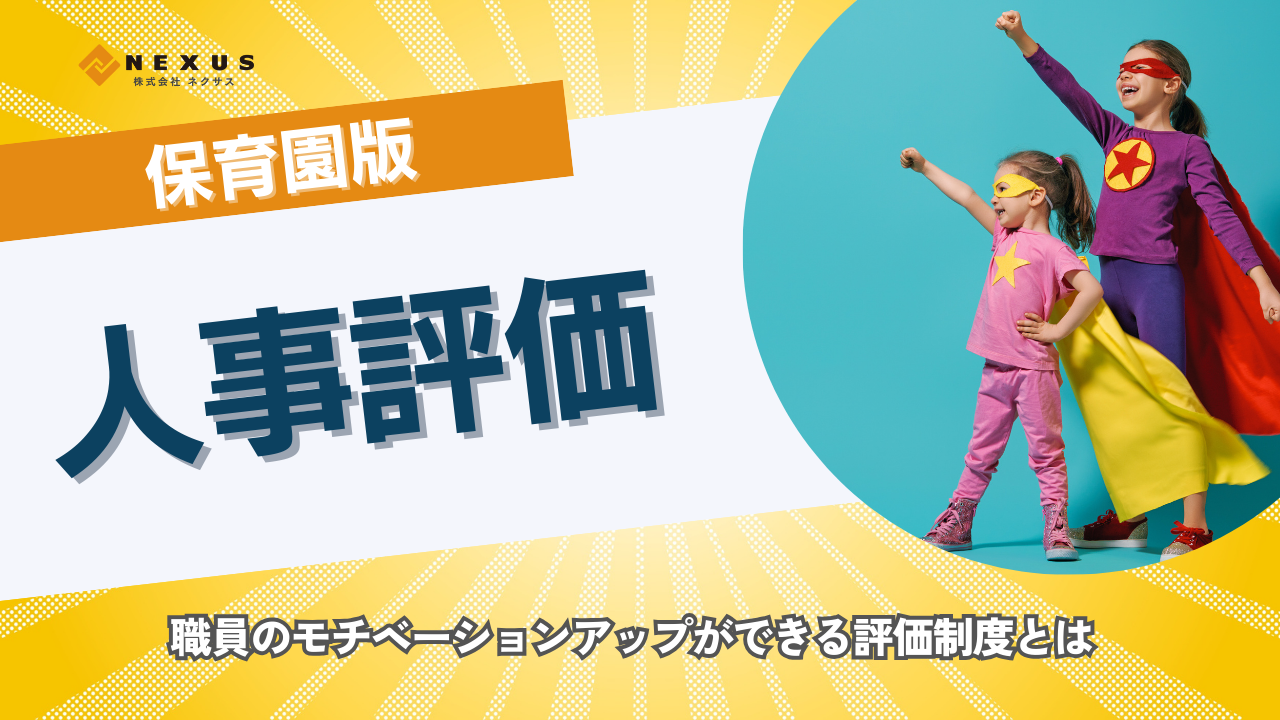
投稿日:2025年9月26日
「人事評価は大切だと思っているけど、実際取り組むのはハードルが高い」と考えている保育園経営者、管理者の方は多いのではないでしょうか。「人事評価=査定」だと考えそれ自体にマイナスイメージを持っている方も少なくないと思います。
このコラムでは、職員に「優劣をつける」のではなく「成長を促す」ことを目的とした人事評価についてお伝えします。職員のモチベーションを高めたいと考えている方にぜひ知っていただきたい内容です。
成果の見えづらい保育園では人事評価はできない?
保育園では、実に多くの「評価」が実施されています。皆さんがはじめに思い浮かぶのはどの「評価」でしょうか。
自己評価ガイドラインで求められている評価、第三者評価、定期的に行われる監査も評価の一種ですよね。
「人事評価」とは、一定期間における職員個人の仕事の実績や能力、姿勢などを評価するものです。職員一人ひとりを見てその仕事ぶりや成長を測るものともいえます。それが給与や賞与、昇給や昇格に連動することで頑張っている人に報いる仕組みが評価制度です。
主な仕事が「保育実践」である保育園では、成果が見えづらく人事評価がしづらいというのが皆さんの大きな悩みではないでしょうか。だから人事評価は行わない、という園もあるでしょう。しかし本当にそれで良いのでしょうか。
評価とはPDCAサイクルのC=Checkに当たります。保育と同様に実践の後には評価がなければ、自分がどれだけ成長できたのか、まだ努力できるところはどこなのか、現状把握することができません。それが続けば仕事の目標や意義を見失い、目の前の仕事をこなすだけになってしまいます。仕事を通して成長したいと思っている職員はモチベーションが下がるでしょうし、頑張っても報われない状況は不満を募らせることにもつながるでしょう。
人事評価は、上手に利用すれば、職員の成長支援やモチベーションアップを図ることができる人材育成の手段の一つです。
では、どうすれば自園でうまくいく評価制度が導入できるのでしょうか。
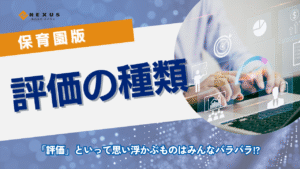
保育園における人事評価の課題
保育園で人事評価がうまくいかない場合にはいくつか理由が考えられますが、最初に挙げた「成果が見えづらいから評価もしづらい」というのは実はうまくいかない理由としては妥当ではありません。
これまで人事評価に取り組んでみたけどやめてしまったという園さんでお聞きする課題を整理してみましょう。
評価の目的が共有されていない
前述したように保育園にはさまざまな評価がある中で、人事評価は何のために行うのか、評価結果は何につながるのか、を職員にも共有していないければ、不信感ややっても意味ないという感想を持たれてしまいます。特に、評価が給与や処遇に反映されるのかどうかということは職員にとっても大事な情報ですから、事前に説明しておきましょう。
「人材育成のため、あくまで本人の成長を促すための評価」という目的が共有ができておらず、「査定の評価」だと受け取られていれば、職員はより良く見せようと過大な評価をつけるかもしれません。逆に、自分の振り返りのチェックリストのようなもので、自己評価のみで上司評価も行わないと説明されていると、「真剣に取り組んでも仕方がない」と思われてしまうかもしれません。
そのような誤解を生まないために、管理者の意図や想いを評価の目的とともに伝え、人事評価が園として重要な位置付けであることを理解してもらい制度を浸透させていかなければなりません。まずは園としての評価の目的をはっきりさせるところから始めましょう。
評価の基準があいまい
何を基準に評価しているのか、がはっきりしないと職員の不満につながります。「どうせ園長先生の好き嫌いで評価してるんですよね」という印象を与えてしまうのです。
また、評価基準があいまいであることは、被評価者である職員だけでなく、評価する側である管理者にとっても評価しづらいでしょう。管理者は公平に評価しているつもりでもそれが伝わらず、誤解を招く元になります。
これは、評価基準の根拠となる「何のために」「何を見て」評価するのかを明示するキャリアパスなどを整備することで解決できます。成果の見えづらい保育という仕事でも、評価軸を可視化することは可能なのです。
頑張っている人を評価してあげたい、という「頑張っている」は園ごとに異なります。私たちの園ではどんな行動、どんな姿が「頑張っている」と評されるのか、それを言語化してみましょう。
評価者の主観で感覚的に評価している
評価者が一人ではなく複数いる園の場合は、それぞれの感覚で評価してしまい人によって評価結果に差が出ることも考えられます。「〇〇先生の評価は厳しいけど〇〇先生は甘い」というような違いが出てしまえば、より人事評価に対する信用が損なわれるでしょう。
人が人を評価する以上、主観を完全に排除することはできません。しかし、偏った主観やその人だけの考えやこだわりならば放置することは望ましくありません。
これは前述の、園としての評価基準を明確にすることや、評価者が学び評価についての理解を深めることで解決することができます。評価者にも育成が必要なのです。
評価も面談も実施しているが形骸化している
人事評価に取り組んでいるがいまいち効果を感じられないという園は、毎年形式的に行うだけでやりっぱなしになってしまってはいないでしょうか。
日々の保育で忙しい中でせっかく時間を取って実践しているのであれば、効果を最大化したいと思うのは当然です。そのためには計画的に評価に取り組むことはもちろん、やってみた評価自体を評価するということも必要です。
人事評価に取り組む年間のプロセスから、評価項目の見直しといった具体的な部分まで、実践たら評価して改善するという一連の流れを作ることが大切です。ただし、コロコロとやることを変えるということにならないように、方針を持って運用を始めることも忘れてはいけません。評価は継続が大事です。
また、保育の忙しさに押されて計画通りに実施しないのも問題です。子どもたちのことが優先なのは理解できますが、やると決めていた時期に評価を行わなかった、面談を一部の職員しか行わなかった、ということがあれば、職員さんたちに「これは優先順位の低いことなんだ」「やらなくてもいいんだ」という間違ったメッセージを伝えることになりかねません。そのためには、無理なく実践できる計画で始めることをおすすめします。
人事評価をやってみたけれど逆に職員のやる気が下がってしまった、離職につながってしまった、不満が出てやめてしまった、というような残念な結果にならないよう、想定される課題をクリアして実践していきましょう。
納得性の高い人事評価の条件
想定される課題を解説するために、評価制度を考える際のポイントを押さえていきましょう。次の要素を検討すると納得性の高い人事評価の実施につながります。
透明性
評価制度は、一般の職員にも理解できるようわかりやすくオープンなものにしましょう。評価内容やプロセスを開示し、どのような基準で、誰が、いつ、どのように評価を行うのかを職員に説明することが重要です。
例えば以下のことを明確にして職員と共有することで、透明性を担保します。
- 評価基準:職員一人ひとりが何をどう頑張ればいいのか示されている
- 評価項目:私たちの園の評価したいポイントが示されている
- 評価者:誰が誰を評価するのか、予め知らされている
- 評価結果:自己評価、上司評価の結果を本人がいつでも閲覧できる
- 評価実施の流れ:年度単位でスケジュール化され確実に実行している
- 双方向の評価:上司から一方的に評価されるのではなく、面談等で自己評価とのギャップを擦り合わせできる
公平性
評価制度を導入する際、職員を公平に評価したい、と皆さん仰います。
ですが、管理者がどんなに公平に評価しているつもりでも、公平かどうか感じるのは、実は本人次第です。
「自分はこんなに頑張っているのに、自分より頑張っていない(ように見える)あの人と同じ評価なのは不公平だ」と個人の主観で公平感は左右されてしまいます。
ですから、評価における公平性は、手続きにおいて担保しましょう。
前述した透明性を高めることが手続きの公平性も高めてくれます。全職員が、同じ「園の評価基準」によって、同じ「評価プロセス」に則って、同じ機会を与えられて評価されること。つまり園として計画的な評価制度を運用することが必要なのです。
一貫性
これは園としての一貫した方針を持って評価制度が設計されていることです。
評価の目的に照らし合わせて、評価方法やプロセスを決めたり、園の基準という共通の指標を持ったりすることで、一貫性のある評価制度になります。そして人材育成を目的とするのであれば、この一貫した評価制度が運用されることで同じ方向に向かって職員を育成することができます。
評価制度を単体で始めたという園もあると思いますが、人事制度は等級制度・評価制度・賃金制度が連動して最も効果を発揮するものなので他の制度についても合わせて検討することがおすすめです。
そして、一貫性という点でもう一つ重要なのは評価者ごとのブレをなくすように努めることです。
園の評価制度と評価基準について、評価者となる全員が同じように理解を深め、同じ方針と視点で評価できることが制度に対する信頼感にもつながります。評価者研修などで学んだり、評価後に評価者同士で擦り合わせを行ったりするのも良いでしょう。
双方向性
双方向性とは、評価が上司評価の押し付けのような一方通行にならないことです。
自己評価と上司評価を行う場合、両者にギャップが生じるのは当たり前のことです。それは視点や視野が違うからです。しかし、そのギャップをそのままにしてはいけません。そのために面談の機会が重要なのです。
面談では、本人の言い分を受け止めた上で、評価者側からはどのような点で評価をしたのか理由を説明します。評価基準や評価項目の理解が不十分ということもありますし、視野が狭く自己評価が高い、逆に謙遜しすぎて自己評価が低いということもあります。
それを面談で丁寧に擦り合わせることは、評価への納得性が高まるとともに、信頼関係を構築するコミュニケーションの機会にもなります。「普段の自分の姿をそこまで見ていてくれたんだ」「自分の頑張りをそんなに認めてくれていたんだ」と直接的に感じられることは嬉しいものですよね。
面談は、できている点・改善点・次の期待をセットで伝えていくことで、職員の目標を明確にしモチベーションを高めることもできます。面談の進め方については以下の記事も参考にしてください。

モチベーションを高める仕組みにするために
評価は成長の定点観測
子どもたちと違って、大人の成長はすぐに気づけるような劇的な変化は多くありません。
しかし、半年前、1年前の自分と比較してみると確かにできるようになっていることが増えているはずです。もちろんできなかったことができるようになっていればわかりやすいですが、以前よりも「時間をかけずにできるようになった」「ミスの回数が減った」「先輩のサポートなしで一通りできた」などの少しの変化も成長に他なりません。
そんな成長を実感するためには、変化が起きていることを知る手段が必要であり、それが人事評価の意義といえます。
定期的な自己評価によって、以前の結果より現在の結果が良くなっていたら自分の成長を感じることができます。また、評価項目は園から求められている姿を示しているので、自分が何を期待されてるのかがわかり、今何が不足しているのか、次は何を頑張ればいいのかがわかります。それは次の目標を定めることにつながるでしょう。
このように、継続的に評価を実施していくことは職員本人が自分の姿を客観的に捉える「定点観測」になるのです。
将来の見通しを持てる
評価制度が計画的な人材育成に基づいたものであるなら、職員は長期的に見た自分の将来像をイメージすることができます。
評価項目が、段階的にレベルの高いものへと変化していけば、それに伴って職員も自分のスキルアップを図ることができます。このレベル分けが等級制度ですが、新人レベルの職員とベテランの職員では求められることが違うはずなので評価項目の難易度も異なります。なので評価シートは新人用、中堅用、ベテラン用、などとレベルに応じて分けることが望ましいといえます。
個人のスキルアップの他に、役職に就くというステップアップも考えられます。5年、10年とこの園で働き続けると自分はどんなキャリアを積んでいけるのか、それが見通せることは職員のやりがいにつながります。
長く働き続けてもずっと変化がない、私はずっとこのままかもしれない、と不安を抱く状態が続くとモチベーションが下がったり離職を考えたりしてしまいます。
自分の将来像が描けるロールモデルがいることも良いですが、園としてのキャリアパスを明示することが必要とされています。
自分の努力次第で変えられるものがある
主体的な保育が主流となるなかで、職員にも主体的であってほしいと皆さん考えておられると思います。ですが、受け身な職員が多くて困っているというご相談が多いのも事実です。
主体的になるための条件の一つとして、自分にコントロールできる余地があるか、が大切だと考えます。
自分が頑張ることによって変化することがある、影響を与えられるとわかれば、努力する甲斐がありますよね。全てが上からの指示で、意見を言ってみても採用されることがない、工夫してみても報われないということが続けば、指示通りに動いた方が楽だと思ってしまうはずです。
ある程度職員に裁量を与え、自分で考えて決めることを増やしていくことが主体的な人材育成につながるのですが、それは評価制度においても同様です。
自分が努力したことによって、昇格した、役職が上がった、給与が上がった、という変化があれば努力が報われることによるモチベーションアップが望めます。一方で、例えば役職に就きたくないと自分が現状維持を望んだから給与や処遇が変わらない、同期でも処遇に差がある、ということも納得できます。自分で選択した、という実感が職員本人にあることが大切なのです。
面談で対話をする
繰り返しになりますが、保育園の評価制度の中で面談は非常に重要です。
一方的に評価結果を伝える場ではなく、自己評価と上司評価のギャップの擦り合わせという対話をすることで双方の納得感を得ることができます。
できていないところだけを指摘したりアドバイスしたりするのではなく、本人が成長を実感できるような働きかけとこれから期待していることを伝え、本人が頑張りたいと思っていることも知れるように対話しましょう。同じ保育者でも、仕事をする上でやりがいを感じる部分は人によって違います。一人ひとりのやりがいを理解できれば普段のマネジメントでも役立つでしょう。
そして普段はなかなか1対1で話せる機会もないと思いますので、この機会に一人ひとりに対して承認と感謝を伝えることができます。それが信頼関係の構築につながります。
職員の成長を促すために保育園で面談は欠かせないのです。
制度を整える暇がないけど何から取り組めばいいか、と聞かれたら、効果的な面談に取り組むことから始めるのをお勧めします。
評価=人材育成の制度
人事評価によって職員のモチベーションを高めたいなら、評価=人材育成の制度と捉える視点が必要です。
その上で、透明性・公平性・一貫性・双方向性を担保した評価制度を整えることです。
それには自園に合った人事制度(の一部としての評価制度)を構築し、職員の成長を促す仕組みづくりに取り組むことをおすすめします。職員にとって納得性の高い仕組みになれば、モチベーション向上や定着率向上にもつながることが期待できます。
私たちの園でこそ活躍できる職員とはどんな姿なのか、その姿を表す行動や能力は何か、それが評価項目として言語化できれば、園の基準に沿って面談を通した成長支援ができるはずです。園が期待する姿に向かってスキルアップする職員が増えれば、それは間違いなく園全体の質の向上につながります。
職員が成長実感を持てる人材育成の制度づくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。
私たちネクサスは、保育施設専門にキャリアパス設計サービスを提供しています。
人事制度を導入したいが何から始めたらいいかわからない、
自園に適した評価制度を作りたい、
などのお悩みがございましたら、まずは無料相談から承ります。
あなたの園に合う、職員が育つための仕組みづくりを一緒に考えてみませんか?