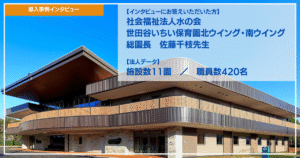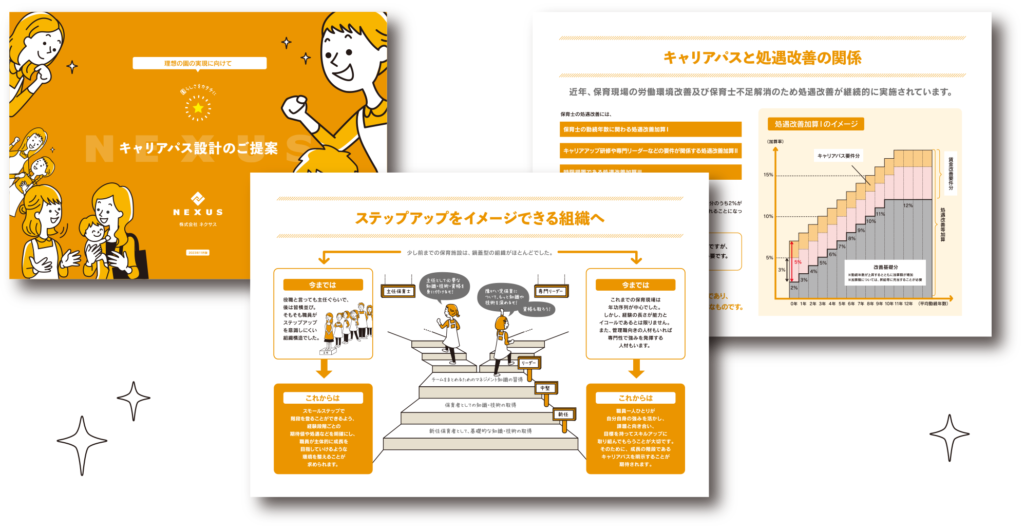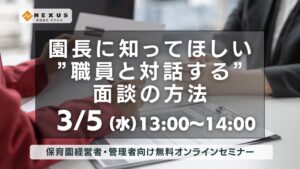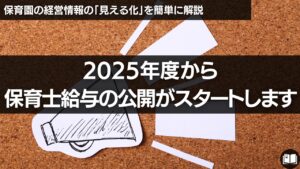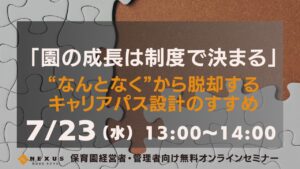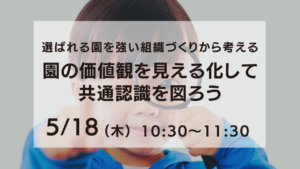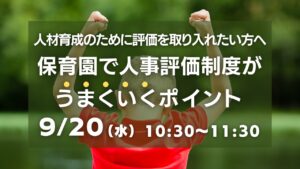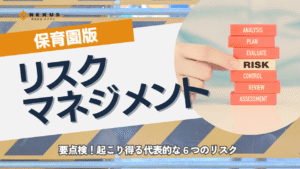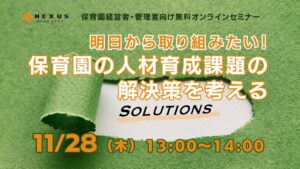キャリアパス制度の設計が完了して終わりではなく保育現場に落とし込んで出来上がった【社会福祉法人宮原ハーモニー 理事長・島村先生にインタビュー】
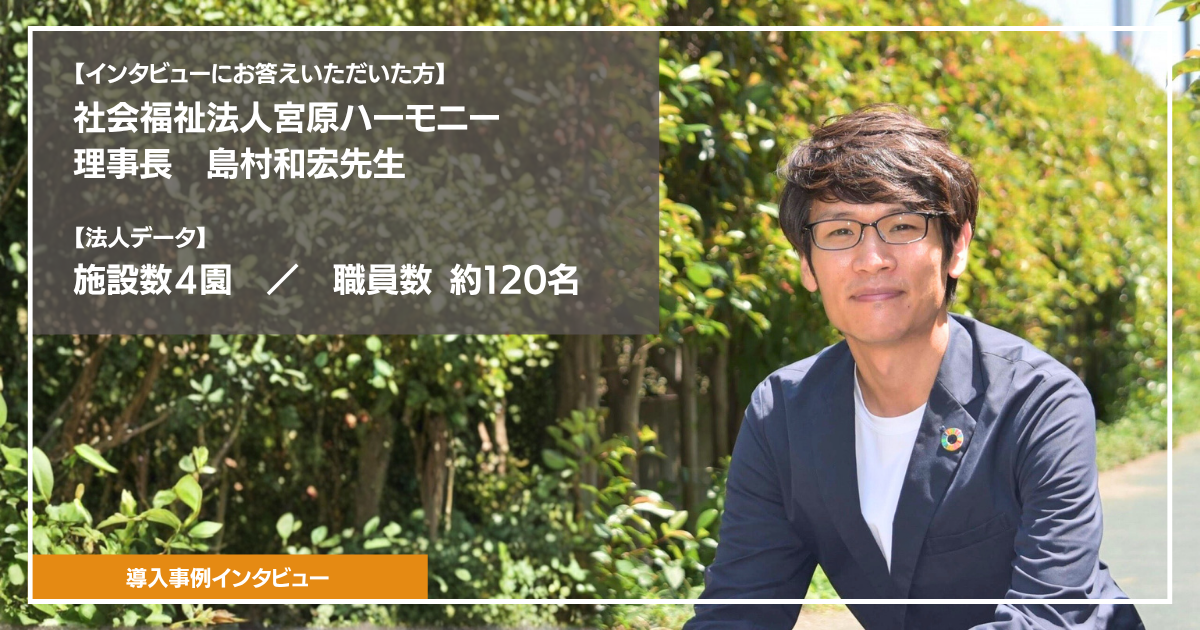

埼玉県さいたま市にある≪社会福祉法人宮原ハーモニー≫は、『やさしい未来を育てよう。』の法人理念を掲げ、保育を通じての社会貢献を使命としております。私たちはひとりの個性を伸ばしながら、みんなで育ち合える保育で、人が人を思いやれる「やさしい未来」を育てていきます。
ネクサスは埼玉県で4園の保育施設を展開する社会福祉法宮原ハーモニーさんへ、キャリアパス設計・運用サポートのサービスをご提供しています。今回は、2021年度と2025年度に実施したキャリアパス制度設計について、考えや今後の運用に向けて展望を伺いました。
【実施・導入実績】
● キャリアパス設計(2021年)
● キャリアパス設計_追加設計(2025年)
2025.10.2
2021年/キャリアパス制度導入のきっかけ
複数施設で共に人材育成を行うために必要な仕組みだと思った
ーー2021年、最初にキャリアパスを導入しようと思われた背景は何でしたか。
当時、キャリアパスの制度を作る必要性を感じて情報収集をしていました。処遇改善等加算の制度は始まっていて主任や副主任やフロアリーダーなどの役職はあったのですが、主任保育士以下の役割や段階というのが明確ではなかったんです。処遇改善等加算をどう分配するかもそうですが、現在私が園長を務めている園の新規開設もあり法人として職員数が増えてきた時期で、系列施設で共に人材育成を行なっていくには必要な仕組みだと思っていました。
ーーその時点での人材育成の課題を解決したいというより、今後のために必要だと考えていたのですね。
そうですね。当時を思い出すと、やはりそういうものが見える化されていないというのは、組織として良くない状態かなと感じていました。仮に自分が保育士として入職した時に、「何年後にどういう役職についているのか」とか「こういうキャリアを描けるんだよ」と示されている方が、将来の見通しが立てられるのではないか、自分なら知りたいなとシンプルに思ったんです。安心して働ける材料になるというか。
だから今は問題が起こっていなくても、共通のものさしがないままではいずれ運営にも限界が来ると考えていた記憶があります。
ーー導入にあたり複数社を検討されたそうですが、ネクサスを選んでいただいた理由を教えてください。
情報収集する中で数社の話を聞きましたが、ネクサスさんは「キャリアパスを人材育成に役立てる」という意図がはっきりしていて、「保育園のキャリアパスに特化している」というのを明確に打ち出している印象がありました。だから、この業界の特殊性を踏まえた設計ができるのではないかと期待が持てました。あとは実際にお話しした時の直感的な部分も大きかったですね。
自分たちの価値や意義がキャリアパス設計を通じて言語化された
ーー2021年の設計では、大元となる保育士のキャリアパスを作りましたが、その時に印象に残っていることはありますか。
4年前の制度づくりはトップダウンで進めました。私以外の園長たちも話し合いには参加していましたが、まだキャリアパスの必要性についての理解が同じではなく、作って運用しながら必要性を認識してもらうことにしました。なので、設計中に制度について完璧に理解したというより、実際に出来上がって「誰々さんはステージいくつで、このステージはこういうことが期待される」というように実際の職員に当てはめて考えることで徐々に具体化でき、制度に対する解像度が上がっていったと思います。制度が完成して終わりではなく、そこから現場に落とし込んで出来上がったという感じですね。
当時を振り返って今思えば…。園長たちは保育現場の経験を経てきた職員たちなのですが、言語化したり構造化したりという作業が難しく、仕組みづくりには苦手意識があったようです。これは保育業務の課題にも通じると思いました。保育は自分で実践と経験を積み重ねて得る知識や視点には強い一方で、それを他者にも伝わるように見える化するということが苦手な人が多いと思います。せっかく蓄積してきたものがあるのにそれを言葉にできないことで、自分たちの価値や意義も伝えづらくなっていました。キャリアパス設計の中でそれをネクサスさんに一緒に言語化していただき形になったので、法人としても分かりやすくなりました。
キャリアパス制度を保育現場へ浸透させる工夫
園を超えたステージごとの研修が制度の共通理解を進めた
ーー現場への導入はどのように進めましたか。
まずはキャリアパスができたということを全体に説明し、さらにステージごとに研修を行って制度の具体的な内容を浸透させるようにしました。4園それぞれの同じステージの職員にオンラインで集まってもらって、そのステージの評価項目の意図を説明し、そのステージではどんな能力や行動が求められているのかを解説しました。所属する園を越えて同じ立場の職員が集まるので、私たちはこういう役割を求められている立場なんだ、という共通理解が進んだと思います。
自己評価だけでなくグループワークで対話することで振り返りが深まる
ーーそれは効果的な取り組みだと思います。とても丁寧に共有されたんですね。
そうですね。やはり、制度を園長たちだけで現場に落とし込むのは難しいと感じ、全職員に制度の意図や背景を丁寧に言葉で伝えることを重視しました。それだけでなく、年に2回自己評価を実施しますが、それぞれの自己評価で終わりにせず、その振り返りも同様にステージごとの研修で行いました。
全園の評価結果をまとめて、法人全体としてこのステージはこういう傾向がある、というのを示し、それを元にグループワークをしてもらっています。この評価項目はほとんどの職員が「できている」にチェックしているから強みだよね、逆にこの項目は「できていない」が多いから個人の課題というだけでなく、法人として次の研修のテーマにした方がいいかもね、というように対話を通じて理解を深めることができていると思います。対話と共感は保育者の強みです。個人の自己評価をした後で同じ立場のみんなと対話することで、視点も増えて振り返りがより深いものになるんですよね。だからこのグループワークのやり方は現場に合っていると思います。
これは今後も続けていこうと思っていますが、同じステージの職員を集めるので年度が変わればステージが変わる職員や新しい職員もいます。それが自分のキャリアアップを考えることにも繋がると期待しています。
ーー現在の制度全体の運用フローを教えてください。
年度の切り替えのタイミングでまずはキャリアパスを見直しています。職員たちの振り返りを元にした評価項目の修正や研修要件など、1年運用すれば変わる部分も出てくるので毎年制度の見直しは必要ですね。そして年度初めに最新のキャリアパスを全体にリリースし、新入職者にも周知します。また先ほど話したステージごとの研修も行い、より具体的に説明しています。
評価は年2回実施し、ステージごとの振り返り研修も行い、それを元に個人面談を行なったり人材育成の研修立案に活かしたりして活用しています。制度は使ってこそ意味があると考え、運用を丁寧に行なっています。
組織のメンバーとして役割を果たすことが保育にもつながっているという意識
ーーキャリアパスを導入してみて、職員さんたちに何か変化はありましたか。
ありますね。それまでステージという概念が無かったですし、それぞれの立場における役割というのが明確になったのはよかったです。私たちの理念を実現するために、園長を始めとする全員にそれぞれの役割があって、組織のメンバーとして役割を果たしていく。それが組織であり、人材育成であり、より良い保育につながるんだという意識は確実に芽生えたと思いますね。
職員たちからも「自分の立ち位置がわかりやすくなった」という話も聞きますし、みんなが同じ仕組みで育つ一体感のようなものも生まれています。ステージごとの研修の効果も大きいと思いますが、園同士の交流や連携が生まれて、違う施設でも同じ法人の一員なんだ、という園を超えた仲間意識のようなものがより強くなったと感じています。
あとは例えばリーダー育成でも、個人の考えでの指導ではなく、法人のキャリアパスに基づく共通言語で話ができるようになりましたね。期待される役割や行動の基準があるので、迷ったときに立ち返れますし振り返りやすくなったというのはあると思います。
2025年/キャリアパス制度の追加設計
園長の役割にもステージが必要だと感じた
ーーそして今回、2025年になって保育士以外のキャリアパスを追加で作成しましたがその経緯を教えてください。
そうですね、実際に保育士のキャリアパスを導入して先生たちにとっての良い影響を肌で感じたので、同じチームで働く他職種の職員にも役割の言語化が必要だと考えました。
実は特に必要性を感じたのは園長という立場に対してでした。4園あると同じ園長でも経験年数に差があります。現場から園長へ上がるケースも増え、園長として求められる役割にも段階(ステージ)が必要だと感じました。現場から見ても、将来的に園長を目指すかどうかは別として、園長になったとしたらこういうことが求められるんだという先が見えていることは大事だと思うんですよね。
ーー今回の制度づくりはいかがでしたか。
正直、4年前と全然違うと思いました。以前はキャリアパスのことがまだよくわかっていなくて、教えていただきながら何とか形にしたという感じでしたが、今回はキャリアパスを実際に導入して私たちの園の制度への理解も深まっていましたし、私自身、法人全体の人材育成に関心が高まっていたようで、あの時と視点が変わっているんだなということを感じました。
4年ぶりの打ち合わせでしたけど、「こういう風にしていきたい」とか「キャリアパスを通じてこういうことを伝えていきたい」というものが自分の中で明確だったので、それを自分の言葉で伝えることができ、スムーズに設計が進んだと思います。
新たなキャリアパスをもとにさらなる学び合いに繋げていきたい
ーーこれからまた新しい制度も含めて見直しと浸透をされていくと思いますが、今後取り組んでいきたいと考えていることはありますか。
まずは今年中に、今回新たに作ったキャリアパスを共有して、これを元にした自己評価も実施する予定です。そして現在は保育士だけにとどまっている研修会を、来年度は他職種も含めて交流研修の形で企画し、みんなの学び合いに繋げていけたらという展望は持っています。
他には賃金制度との連動についても考えています。キャリアパスは人材育成を重視して取り入れているので、現時点では連動させていませんが、将来的に組織全体のレベルアップへ繋げていくためには必要だと感じています。ただし評価者のスキル向上や項目のブラッシュアップを進めた上で慎重に検討したいと思っています。
キャリアパス導入を考えている保育施設へ
想いが言語化されると自分もその言葉を使えるようになる
ーー最後に、これからキャリアパス制度を導入したいと考えている園さんに対してメッセージをいただけますか。
人材育成に悩んでいる園さんは、絶対にお願いした方がいいと思います。
みなさん、園として目指しているものや大切にしている価値観や考えというのは自分の中にあると思うんですが、それを言葉にするって本当に難しいんですよね。それを専門家であるネクサスさんに依頼すれば、例えば「うちの園の職員にはこういう力が必要だと思うんだよね」、「こういうことを考えているんです」と漠然としたものでも、評価項目レベルで具体的に言語化してくださるんです。「そう、そういうことが言いたかった」とこちらの意を汲んでくれるというか。
そして言語化してもらえると、自分自身もその言葉を使えるようになるんです。そうすれば言葉が圧倒的に増えていきますし、言葉って少し間違えるとネガティブに伝わってしまうと思うんですが、そういう部分もポジティブな言葉に変換して伝えてくださるので、管理者自身の学びにもなります。キャリアパスという制度自体の重要性ももちろんあるんですが、私としては管理者の想いを言葉にするという制度づくりのプロセスが、結果として制度を法人全体に浸透させていくことに繋がると感じました。
これだけ人材不足と言われている中で、いかに園の職員の可能性と強みを信じて育成していけるか。それが今後選ばれるポイントになると思うので、園の想いを反映した制度を絶対に導入した方がいいと思いますね。
私たちも今後ブラッシュアップを重ねながら、人を育てるように制度も育てていきたいと思います。
―― インタビューは以上です。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。今後も制度のブラッシュアップをサポートさせていただきます!